
第26回春季大会報告:ラウンドテーブル
C2:国際協力に若者の活力を取り入れるために:外務省・JICAからの視座 開催日時:6月21日11:10 - 13:10 聴講人数:約25名 座長・...
Recent Updates

C2:国際協力に若者の活力を取り入れるために:外務省・JICAからの視座 開催日時:6月21日11:10 - 13:10 聴講人数:約25名 座長・...

この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。

この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。

この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。

2024年度活動報告 1.国際開発学会東海支部(JASID東海)・国際ビジネス研究学会中部部会 共催講演会 「現地での事業展開を通して見たインド・中...

Planning and Management: JASID Reasonable Accommodation 障害を持つ会員への合理的配慮について...
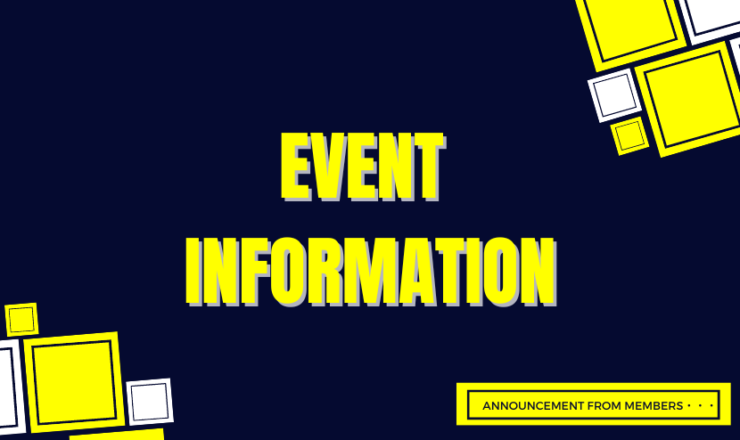
この度、2024年12月6日(金)に対面形式によるイベントを開催することになりました。 参加ご希望の方は下記のフォームに事前登録をお願いします。 W...

“International Symposium: Exploring Global and Local Dynamics on Gen...

活動報告:2023年10月から2024年6月 1.国際開発学会東海支部(JASID東海)・国際ビジネス研究学会中部部会 共催講演会 「現地での事業...

一般口頭発表 1C:教育(日本語) 座長:小川 啓一(神戸大学) コメンテーター:坂上 勝基(神戸大学)、黒田 一雄(早稲田大学) 2023年11...

“Journey Towards Gender Equality in Kenya: Exploring the Intersectio...

東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所では、2023年6月24日(土曜)に、「海外学術調査フォーラム」を、以下の通り対面にて開催します。 本フ...
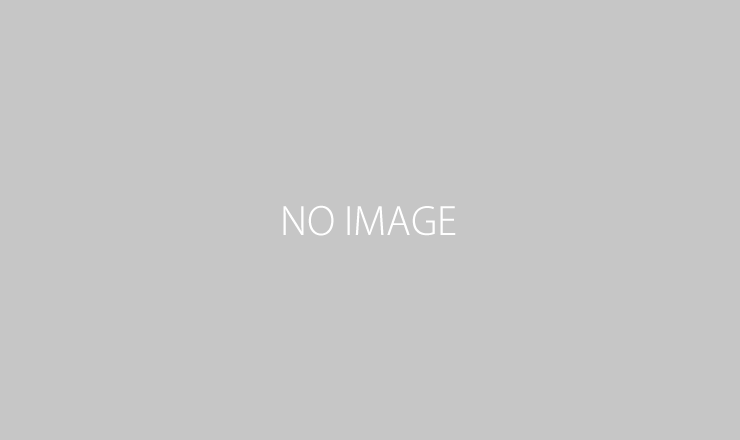
国際開発学会会員 各位 日本学術振興会より国際開発学会に「第14回(令和5(2023)年度)日本学術振興会 育志賞」受賞候補者の推薦について依頼が来...

ラウンドテーブル C-1.授業という開発実践 ー わたしたちはどんな「人材」を「育成」するのか 発表者 (報告:池見 真由) C-2.Adaptiv...

P. 前夜祭 現代アフリカの開発における課題―危機下の市民生活から 前夜祭の趣旨は以下の通りである。サハラ以南アフリカの多くの地域では、独立を経験し...

名古屋市の徳林寺は、コロナ禍で帰国が困難になったベトナム人らを長期にわたって受け入れた。映像人類学者で移民研究者でもあるディペシュ・カレルは、寺にや...

世界展開力強化事業の一環として、ダルエスサラーム大学ならびにネルソン・マンデラ科学術大学院大学の教員と協働で、以下のオンライン・シンポジウムを実施し...

第11期、最初の1年を振り返って 国際開発学会の皆様、こんにちは。この間、コロナに関連して様々な経済的、精神的苦境に立たされてきた皆様には心よりお見...

夏以降、賞選考委員会の業務が本格化してきました。 今年度の学会賞の公募が6月末を締め切りに進められ、その後、秋口から選考審査を進めてきました。11月...