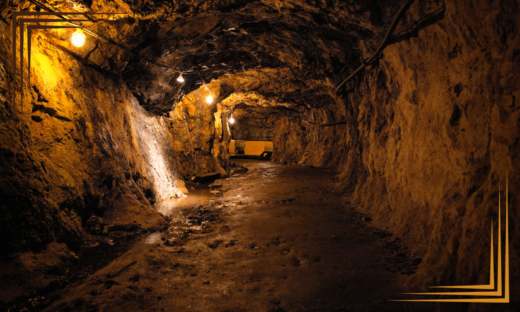第26回春季大会:プレナリー

包摂的開発を実践する国家の作り方: 北海道からの提言
大会プログラム最後の企画として開催されたプレナリーセッションは、「包摂的開発を実践する国家の作り方: 北海道からの提言」と題して、北海道独自の社会構成や自然環境、開発の歴史に基づいた研究や実践報告が行われた。
髙橋彩北大理事・副学長による挨拶のあとで、司会の鍋島孝子北大大会実行委員長が趣旨説明を行った。開発から取り残された人々が獲得した権利を反故にする揺り戻しや、環境問題と資源争奪戦となって現れている昨今、このような動向に異議を唱え、人権の保障や幸福追求(ウェルビーイングやSDGs、人間の安全保障を含む)などを実現した方が、持続的な政治経済の安定を得られ現実的であると、私達は実証できるだろうか。会員には、北海道の事例を各テーマや各フィールドと比較し、それに応用してほしい。
「食料安全保障と『食の民主主義』」
(北海道大学大学院 農学研究院 准教授 清水池 義治)
清水池義治准教授は、北海道の農業が神格化されていることを問題視し、実は、日本全体の食料供給を支える従属的な立場であることを検証した。それは、開拓時代に北海道の農業が国家の農業政策と直結しており、戦後の米国中心の余剰フードレジームのもとで輸入飼料依存の加工型畜産となったためだと言う。実際に食料自給率や酪農家戸数をグラフで示し、牧草の主産地にも関わらず、酪農経営の大規模化によって輸入飼料への依存が高まる実態を明らかにした。そうなると、当然ながら大規模経営ほど飼料高騰の影響が大きくなり、他都府県への生乳輸送もコストがかかるようになった。このような問題を解決しようと、酪農家と地元住民による製品開発が試みられているが、もっと政策として国民の食料安全保障の争点に切り込んでいける食の民主主義」(food democracy)として、自らの選択に基づき、健康的で人間らしく持続可能な食生活を実現していくことが重要である。食料安全保障は「持続可能性」「主体性」「安全性」「供給」「アクセス」「利用(well-being)」の概念で構成される。Food Policy Council(食料政策会議):消費者から「食市民(food-citizen)」へと変わる政治イノベーションが肝要であり、全ての市民が世界・国家・地域・個人のレベルで農業と食のあり方を決定する力を持つことをagencyの概念とした。
北海道の酪農の実態を指摘した上で、コミュニティーの参加による国家の農業政策の実現が具体的に見える報告であった。
「自然エネルギーで北海道独立?」
(特定非営利活動法人(NPO) 北海道グリーンファンド 理事長 鈴木 亨)
本発表で鈴木亨理事長は、NPO北海道グリーンファンド及びグループによる風力発電や畜産バイオガス、小水力発電、木質バイオガスボイラーの活動を紹介しながら、市民自ら創り上げていく持続可能な社会を目指すことを目的に、再生エネルギーの全体的な動向と政策について語った。例えば市民が出資して全国で進行中のプロジェクトである市民風車は、自然エネルギーの啓発活動であると同時に、地域に存在する未利用な自然エネルギーを地域住民の手で地域のために活かす事業であり、コミュニティの意思決定や利益還元がなされる。例えば北海道では石狩市内小中学校への市民風車の電気の供給や同市厚田区での地域活性化の取り組みへの支援などの事例を、その他、生協と連携授業した秋田と青森の事例を紹介した。さらに、本報告はグローバルな地球温暖化と、日本のエネルギー自給率の問題、世界と日本の電力と電気代の推移を展開する。そして今年2月、政府が閣議決定した第7次エネルギー基本計画では再生可能エネルギーの割合を2023年度22%から2040年には4~5割にするとしているが、2023年にCOP28で合意された世界全体で再エネ3倍の目標に貢献するとはいえないかなり低い伸び率となっている。北海道の再エネの可能性(導入ポテンシャル)は全国随一と言え、日本がカーボンニュートラルを実現できるかどうかは、北海道での取り組みによる。北海道で再エネを広げていくためには、道内企業、自治体による再エネの取り組みや再エネ事業への市民参加をひろげ、地域で作ったエネルギーを地域で利用してその利益を地域に再投資する地域循環型経済を目指すことが必要だ。
NPOによる具体的な事業説明だけにとどまらず、エルネギー政策の現状分析と政策提言が結びついた報告となった。
「学生サークルの長期モニタリングから見えてきたヒグマと人間の関わり」
(北海道大学ヒグマ研究グループ代表 北海道大学法学部3年 大部 鏡悟
北海道大学理学部2年 福島 拓)
まず、大部さんからこの学生グループについての紹介があった。同グループはヒグマについて、春から秋にかけて天塩研究林で痕跡記憶をとり、夏には大雪山系黒岳で行動観察、冬には札幌近郊で冬眠穴捜索をしている。隊長とメンバーが自由に計画を立てて踏査し、それを報告する工程を行なっている。足跡や糞、背こすり痕などを見つけ、『ひぐま通信』に報告を掲載している。これは半世紀にわたる貴重なデータを蓄積したもので、このような調査からヒグマ生態学の専門家を多く輩出した。次に、ヒグマの管理政策についての説明に移り、戦前には開拓が進むにつれて駆除が奨励されたが、戦後の特に1966年から90年までは冬眠終了時の「春グマ駆除」が実施された。平成になると、保護政策と科学的管理に舵がきられた。こういった政策方針に対して、学生によるヒグマ個体群のモニタリングから得られた教訓は一定の貢献と役割を果たしたと言える。例えば、春グマ駆除を廃止したところ、痕跡発見率は増えたので、駆除政策の個体密度への影響を実証したこととなった。尚、学生グループによる調査のメリットは、時間や予算の制約がなく、ヒグマへの興味と調査のモチベーションを維持でき、確立された方法で長期に渡って調査できている。現在、管理政策は再び転換期に来ているので、今後も調査を継続してデータの推移を見ていきたい。福島さんからは、山の実のなり具合と農作物の被害について説明があった。ヒグマの食性はその場にあるものを食べる日和見的食性である。そして昨今、人身被害と農業被害が増えている状況の中、ミズナラの資源量を調べ、糞を採取して内容物を分析した結果、ヒグマは9月には収穫期のデントコーンを多く食べ、9月末から10月には山でミズナラを食べていることが分かった。このように、人間の農業生産がヒグマの食性行動に影響を与えていることが立証された。これからも人間の行為とヒグマの因果関係を調べ、ヒグマの生態のより良い理解に繋がるよう、調査を続けたい。
学生の研究対象への熱意と地道さに共感が湧き、培われたきた科学的な手法と今後の活動が期待される。
「開発とアイヌ」
(アイヌ舞踏家 原田 公久枝)
原田さんは、アイヌの開拓時代からの苦難の民族の歴史とともに、個人に降りかかった現代の差別意識をエピソードとともに語って下さった。それはユーモアに溢れているものの、民族と個人の尊厳を求める信念と怒りがほとばしるものであった。開発の政策や大義名分の下、アイヌを旧土人法によって「獣」から「土人」に格上げしたものの同化政策で、1899年から1997年の125年間、アイヌがアイヌらしく暮らす方法を奪ってしまった。「私はつい28年前まで土人だったのよ」とあきれ気味に仰った。2008年、衆参両議院で「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」が採択され、2019年に「アイヌ施策推進法」が成立したが、国の多様性を確保するために利用しているように見える。また、2008年の決議にもかかわらず、未だ先住民族とは認められていない。「アイヌの誇り」の回復を謳っているけれど、開発の期間、旧土人として全てを奪われて、今更どのように回復すればいいのか。アイヌの踊りや歌、刺繍を実践していたらいいと言うのか。原田さんは日本の学校教育に入れられ、虐められ、それでもアイヌのことを学ぼうとしたが、それはとても難しかった。また、「純粋なアイヌなんていないんでしょ」とか、アイヌの側に立つと言ってくる日本人は、これまでの差別のことをどう思っているのか。ただ、アイヌを特別なものとして妄想して、現代のアイヌの人たちの生活を見て勝手にがっかりしているのではないのか。それから、オリンピック・パラリンピックや万博などのイベントで踊りを披露する話があると、「和人と手を携えよう」と言われたり、カルチャーセンターと同じような認識だったりすると、違和感を覚える。和人との分断やアイヌ同士の分断の中、さらには生活や老後の心配をしながら、一方で幸せも感じながら必死で生きている。
原稿は読み終えたものの、最近、違和感を持った、「頭にきた」アイヌに対する言動のエピソードの紹介もあった。会場は、原田さんの説得力ある視点や指摘、さらには感受性豊かなエピソード、苦難や差別を乗り越えるユーモアと生命力に感銘を受け、学会としては異例の感動に満ちた。
コメント
(JICAブータン事務所 所長 木全 洋一郎)
(北海道大学 北極域研究センター 研究員 加藤 知愛)
次に二人の討論者から以下のように登壇報告の内容の総括や、さらなる問題の指摘などを経て、本テーマの理解と応用がなされた。
まず加藤会員は、国際開発の概念の中で、包摂的開発の概念を明らかにした。それは、開発課題(格差拡大、気候変動など)への反省から生まれた新しく、あらゆる社会における 「排除」を克服する普遍的なアプローチで、経済成長を公平に分配し、多様な人々が開発プロセスと成果に参画・享受できる社会の実現を目的とする。この概念を考慮すると各報告のキーワードが明らかになり、それぞれ、食料生産・流通・消費における公平性と持続可能性、エネルギーの自立的な地域経済システムの形成、人間と自然環境の調和、歴史的正義の実現などのパースペクティブが浮かび上がってきた。「包摂的開発」は、従来の国際開発議論における「社会的包摂」が主に貧困、ジェンダー、教育、保健など人間中心的な開発アプローチであったことに対して、「自然環境や地域資源との関係性」にまで踏み込んで開発を思考するアプローチであることを指摘した。
木全会員はブータンからオンラインで、コメントと国際的な視点で包括的かつ具体的な質問をしてくれた。同会員は開発を考える上で、農業とエネルギーについて、地域の文脈に合わせた開発とグローバルな規模の開発をどのように考えるかを、また、クマとアイヌの問題については、国やグローバルな開発に代わるあり方を示唆しているのではないかと問題提起した。また、農業から見たエルネギーのあり方、またはその逆、クマと農業被害の問題、アイヌと野生動物との共生など、各テーマは関係性があることを指摘した。そして同会員は、かつての北海道での経験から、東京や札幌の都市部の人々は各課題にどのように向き合えば良いか考える当事者意識が重要だと締め括った。
登壇者は二人のコメントと質問に、またフロアからの質問用紙にそれぞれ自由に、または答えやすい点から回答してもらった。
各報告の中の概念の確認やその具体例などへの質問がなされた。また、クマ研に入ろうと思った動機が聞かれたり、「ヒクマから見た良い人間とは?」といった質問も出た。それは、ヒグマに出会わない人間だそうだ。NPOとして太陽光についての言及がなかったのは何故かの質問も出た。また、電力事業者の経営コスト問題についての具体的な質問もあった。
プレナリーの参加者は約200人にのぼり、フロアからの質問用紙は、複数の質問が書かれた15枚であった。最後に、山田肖子国際開発学会会長から登壇者の報告への感銘の言葉と共に閉会の挨拶をいただいた。多少、オンラインの回線や、オンラインの翻訳機能の不備など、技術的には参加者にお詫びしなければならなかったが、会場と登壇者の活発で有益な討論を得て、無事に終了することができた。