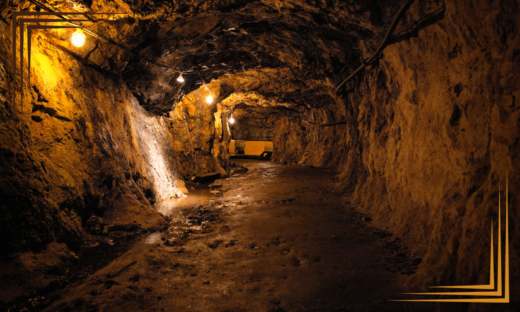関西支部(2025年8月)

関西支部:2025年度6月末活動報告
2025年度、関西支部ではハイブリットによる定期的な研究会の開催を計画しました。本支部が開催する研究会では、国際開発・国際協力に関するさまざまな分野の専門家を招聘し、教育開発、災害対策、水の保障、環境保全などを含むグローバルな開発問題に関連した多様なテーマに関する議論を精力的に展開していくことを目的としています。
上記活動目標に基づき、2024年11月から2025年6月までに実施された研究会についてご報告させていただきます。
第179回研究会【日時:2024年10月29日(火)17:00-19:00】【言語:英語】
発表テーマ:
Preparing Thai Teachers for Diverse Classrooms: National Efforts and Global Implications
発表者:
Assistant Professor Nannaphat Saenghong, Faculty of Education, Chiang Mai University / Visiting Professor, Graduate School of International Cooperation Studies (GSICS), Kobe University
参加人数:
44名(対面38名、オンライン6名)
概要:
本研究会では、チェンマイ大学助教授・神戸大学客員教授のNannaphat Saenghong氏を招聘し、「Preparing Thai Teachers for Diverse Classrooms: National Efforts and Global Implications」を題目とした講演が行われた。Nannaphat氏はまず、タイにおける教師教育制度の基礎情報として、教師教育のカリキュラムの内訳や教育政策、現在の課題などについて言及された。次に、タイが抱える文化的背景として、およそ62を超える民族集団が定住していることを指摘し、多様な民族的背景の下、公教育はどのように運営されるべきなのか、教師はどのように訓練されるべきなのかについて解説された。特に、多様な民族的文化のもとでタイの教師が直面している困難として、言語的障壁や文化的感受性を例に挙げ、その上で多様な子どもたちを包摂する学校の実現には、多文化主義の考え(Multiculturalism)や多文化教育(Multicultural Education)が鍵となることを強調された。また、多文化教育の実現に向けて教師教育が果たすべき役割として、教師の多文化理解の促進や教室での多様性に向けた実践的訓練についても述べられた。さらに、タイ政府の多文化共生への政策的変遷についても概観され、2017年の憲法改定を経て、タイ政府が多文化共生実現に向けての前向きな姿勢を正式に表明したことについても触れた。しかしながら、依然として多文化共生に向けての困難は続いており、多文化共生の内容を含む教師教育のカリキュラム開発の難しさ、憲法や法律レベルで多文化共生を提言する文言が限られていることなどが挙げられた。研究会の終盤では、多文化共生に向けた教師教育と持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals=SDGs)との関係について、目標4「質の高い教育をみんなに」、目標5「ジェンダー平等を実現しよう」、目標10「人や国の不平等をなくそう」の観点から解説された。ここでも、多文化共生な社会の実現に向けた重要な鍵として教師教育が挙げられた。喫緊の開発課題に立ち向かい、「誰ひとり取り残さない」包摂的な社会の実現に向け、教師教育の重要性について学ぶ大変貴重な研究会となった。
第180回研究会【日時:2024年12月20日(金)14:15-15:30】【言語:英語】
発表テーマ:
The Role of Socio-economic Development Planning in Lao PDR
発表者:
H.E. Phonevanh Havong. Vice Minister, Department of Planning, Ministry of Planning and Investment of Lao PDR
参加人数:
68名(対面51名、オンライン17名)
概要:
本研究会では、ラオス計画投資副大臣のH.E. Phonevanh Havong氏を招聘し、「The Role of Socio-economic Development Planning in Lao PDR」をテーマとした講演を行っていただいた。H.E. Phonevanh Havong氏は、講演の冒頭でラオス人民民主共和国における国家社会経済開発計画の歴史を振り返り、これまでの進捗状況や成果について述べられた。そして、近年直面している喫緊の課題として、経済成長の減速、インフラの未整備、地域間格差、そして外部経済環境の変化への対応など、具体的な問題点を列挙し、その背景について詳しく説明された。続いて、H.E. Phonevanh Havong氏は今後5年間にわたる国家社会経済開発計画の方向性について概観された。特に、持続可能な経済成長の実現、人材育成、投資促進、貧困削減、デジタル化の推進など、重点分野を挙げ、具体的な政策目標と実行計画について言及された。さらに、講演後の討論セッションでは、本学の名誉教授である豊田敏久先生が討論者として登壇し、ラオス人民民主共和国の今後の展望についてコメントされた。豊田先生は、ラオスが直面する課題に対する解決策や今後の発展の可能性について見解を述べ、ラオス経済の持続的発展には戦略的な財政金融政策が不可欠であることを強調された。本研究会は、ラオスの発展計画に対する理解を深めるとともに、国際協力の重要性を再認識する貴重な機会となった。
関西支部
支部長:小川啓一(神戸大学)
副支部長:關谷武司(関西学院大学)