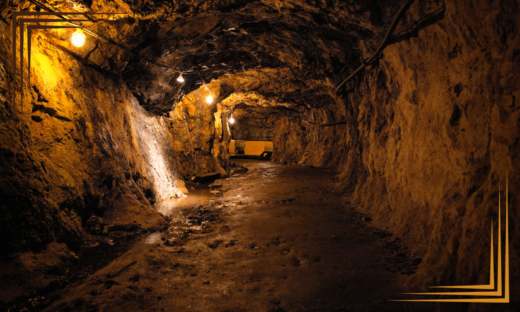第26回春季大会報告:企画セッション

座長報告:企画セッション
A2:BPS Special Session Bridging Data and Policy Study: Enhancing Socioeconomic Research in Indonesia through Badan Pusat Statistik
- 開催日時 6月21日11:10 - 13:10
- 聴講人数:約5名
- 座長・企画責任者: Mitsuhiko Kataoka (Rikkyo University)
- コメンテーター・討論者:片岡光彦(立教大学)、Pham Anh Ton (Rikkyo University/ Stata Bank of Vietnam)
【第一発表】The Impact of Educational Assistance on Child Labor Issues in Indonesia
発表者
- Annisa Nur Purnama (Ms.) (BPS (Badan Pusat Statistik), Indonesia)
コメント・応答
児童労働を「週1時間以上」で定義すると、他の基準(例:週12時間以上)では結果が変わる可能性がある。観察されない交絡の影響が懸念される。
児童労働の割合(0.49%)や労働時間(週14分)の減少は統計的に有意だが、政策的な意義は慎重に評価すべきである。
また、対象者がPIPのみを受けていたのか、他の支援(PKHなど)も含まれていたのかを明確にし、影響を適切に統制する必要がある。
【第二発表】 The Role of Education and Internet Usage in Shaping Household Inequality in Indonesia: A Shapley Decomposition Analysis
発表者
- Ni Kadek Dian Pitriyani (Ms.) (BPS (Badan Pusat Statistik), Indonesia)
コメント・応答
サンプル・バイアスを考慮した分析手法を検討してはどうか?
インターネットの利用の有無が家計消費に影響するとしているが、逆の因果は検討できないか?先行研究などので言及してほうがようのでは?
【第三発表】Is Poverty Decomposition Change Before, During, and Recovery Period of the COVID-19 Pandemic? A Study of Districts in Indonesia
発表者
- Dwi Indri Arieska (Ms.) (BPS (Badan Pusat Statistik), Indonesia)
コメント・応答
空間データ分析の拡張として、局所モランの I を用いてパンデミック期の貧困の空間的関連とその変化を可視化してはどうか?
将来の研究の方向性として、地区ごとの貧困変化(ΔPᵢ)を説明変数 Xᵢ と空間ラグ wᵢ に基づく回帰モデルで分析することで、空間ラグモデルの活用を検討してはどうか?
総括
途上国のデータを用いた実証研究では、データの制約は避けられない課題である。その程度は国によって異なるが、インドネシアでは過去10年間でデータのアクセシビリティが著しく向上し、より信頼性の高い研究が可能になっている。データの利用の拡大は、堅実な研究を促進し、頑健なエビデンスを提供し、より良い政策決定につながるという好循環を生み出している。
データが公共財である以上、こうした研究成果も公共財であり、インドネシアに限らず、多くの開発途上国でこの有益な循環が広がることが期待される。
報告者(所属):Mitsuhiko Kataoka (Rikkyo University)
A3:中東・北アフリカにおける包摂的開発と食料安全保障:エジプト・チュニジア・ヨルダンの事例から
- 開催日時:6月21日14:10 - 16:10
- 聴講人数:約12名
- 座長・企画責任者:井堂有子(新潟国際情報大学)
- コメンテーター・討論者 :佐藤寛(開発社会学舎)
【第一発表】エジプトの食料安全保障と地下水開発・砂漠開墾 ―エジプト西部沙漠の事例―
発表者
- 岩崎えり奈(上智大学)
コメント・応答
- (質問やコメント)
- 沙漠の耕地化を国民は支持しているのか?
- 化石水の枯渇の問題、水利用の持続可能性はどうなっているのか?エジプト全体での穀物生産のシェアは?
- 農業問題は教育から変えていく必要があると感じる。エジプトの社会起業によるヘリオポリスの大学では「小さな農業」を重視する農学部が設置され、大学教育から農業に理解を持つ若者たちを増やそうとしている。
- (応答)
- 砂漠の耕地化への国民の支持は分かれている(食糧増産のために支持する人々もいれば、水資源の問題を懸念する人々もいる)。
- 水文学者によると、貯水量の実態は不明で、世界最大規模のヌビア砂岩帯水層がどれくらい持続しうるのかは研究者によって見解が分かれる。現在年間で3メートル低下している地下水の水位をこれ以上下がらないようにするしかない、という危機感は共有されている。
【第二発表】チュニジア乾燥地域における農業生産の課題と展望 ―気候変動の影響と新技術導入の実現可能性―
発表者
- 山中達也(駒澤大学)
コメント・応答
- (質問やコメント)
- 欧州への輸出で活路が見いだされるのか、国民は受け入れているのか。
- 「アグリビジネス」の定義について伺いたい。国連UNIDOでは、小規模農業ビジネスも含めて「アグリビジネス」と定義しているが、御講演では「従属」といった表現も含め否定的な捉え方がなされているような印象を受けたが。
- 「農業の脆弱性」というのはどういう意味か?
- (応答)
- 「アグリビジネス」の定義は一様ではないが、本報告では大規模な事業主体による農業生産・欧州市場等への輸出を指しており、地元に根差した農民たちの世界とは別次元の経済活動(グローバル・ファームへのチュニジア農業の従属的関係)と理解している。
- 「農業の脆弱性」には、チュニジア農業が直面している深刻な水ストレスや気象条件等の問題を含めている。
【第三発表】ヨルダンの食糧安全保障と難民受け入れ
発表者
- 臼杵悠(東京外国語大学)
コメント・応答
- (質問やコメント)
- 食糧補助金の対象として難民と自国民への扱いについて。
- ヨルダンの小麦輸入元としてルーマニアが上位にきていたが、2023年はウクライナ産小麦がルーマニア経由で輸入されていたのではないか。
- ヨルダンではマフラブ等での小農規模レベルでの改善努力の事例があると思うが。
- (応答)
- 自国民と難民双方を食糧補助金の対象とすれば、政府が自国民からの不満を受けることは避けられないので、難民に支援が偏らないように気をつけている。ただし、ヨルダンは難民を受け入れているからこそ、国外からの財政的援助を獲得できた面もあるため、今後も自国民だけではなく難民への援助もある程度続けていくのではないかと考えている。
総括
本企画セッションでは御報告者3名より3か国の事例を通じて多様な論点をご提示頂いた。ディスカッサントの佐藤寛先生より「中東・北アフリカの食料安全保障という大きな枠組みでのセッションで、広範囲な問題群―気候・ストレス、IMF勧告による食糧補助金削減と暴動、水・土地の制約と自給・増産の難しさ、乱開発の問題、貧困削減との関係性、フードレジーム論での位置付け等―が見えてきたが、ここからどのような方向性で共同研究を進めていくのか」とのご質問を頂いた。また、今回限られたオーディエンスではあったが、中東・アフリカ地域の食糧・農業問題の研究者、事業運営に携わる国連関係の方々のご参加と貴重な御質問やコメントも頂いた。いずれも非常に重要なご指摘であり、今後個別・共同研究を進めていく上で参考にさせて頂きたいと考えている。皆様に感謝申し上げたい。
報告者(所属):井堂有子(新潟国際情報大学)
B1:労働移民の送出国と受入国の連携による技能移転・人材育成の可能性 ―東南アジアから日本への移民の主体性とキャリア形成の視点から
- 開催日時 6月21日 9:00 - 11:00
- 聴講人数:約15名
- 座長:加藤 丈太郎(明治学院大学)
- 企画責任者:石丸 大輝(国際協力機構)
- コメンテーター・討論者:加藤 丈太郎(明治学院大学)、松下 奈美子(鈴鹿大学)
【第一発表】移住ブローカーの排除から包摂へ ―“移住インフラ”から考える日本の対ベトナム開発協力
発表者
- 石丸大輝(国際協力機構)
コメント・応答
- 移住ブローカーを「包摂」から捉えるのは、日本の移民研究において斬新な試みである。
- 「移住インフラ」を用いることで、規制インフラと商業インフラの相互作用に着目することが可能となった。
- 日本の国際協力政策と移住労働を結びつけて論じており、開発研究と移民研究を架橋するテーマ設定が評価できる。
- 通常ネガティブに捉えられがちな「移住ブローカー」を、単なる搾取的存在ではなく「移住インフラ」として再評価する視点や、規範的判断ではなく現実的な制度運用のメカニズムを把握しようとする分析姿勢には、問題設定の独自性が評価できる。
- 制度設計と現場での実践の間にある「乖離」を「制度的包摂の余白」と捉える視点は、開発協力における柔軟性や中間支援の重要性を示唆している。
- ブローカーの位置づけに関して、単なる善悪の二項対立ではなく、制度と制度外の“連続性”や“相補性”を意識した整理が試みられている。
- ベトナムの送出制度や日本の制度的対応に関して、信頼性を備えた事例分析が評価できる。
- ベトナムにおける「政策と実態のギャップ」について論じる必要がある。(例:技能実習制度におけるブローカーと送出機関の連携について、どのような課題があるのかを明確にする。)
- 移民自身がなぜ「協働型インフラ」の主体となり得るのかの論拠が必要。「移住インフラ」論で「移民の主体性」を捉えることには限界がある。→他の分析枠組みも、今後は検討する。
- 「移住インフラ」の概念が持つ階層性がやや不明瞭。(ブローカーの中にも搾取的な業者と献身的な支援者が混在しているが、それらの差異や位置づけはどうするのか。)「移住インフラ」として包摂すべき実践と、制度から排除すべき実践の線引きは、誰がどのような基準で判断するべきか。→ブローカーの正規化を試みたインドネシア事例が参考となり、要検討。
- 日本のODAや制度に注目する一方、ベトナムの送出政策、またはブローカーを黙認する構造への分析がやや弱い。送出国の海外労働戦略、地方の送出圧力との関係にも触れるとよい。(例:ベトナムにおいて、ブローカーがどう制度的に“容認”されているのか。)
- 「協働型インフラ」の事例として、首都圏の大学での取り組みを上げたが、リソースへのアクセスが厳しい地方部の高校・専門学校で実践する方が有意義。→然り。地方省の農業高校との協力も実践してきた。個別事例の積み重ねのほか、政策レベルでの実践も検討する。
- 需給ギャップの観点で見れば、ベトナムから日本への労働移民の数は右肩下がりであり、将来的な可能性の高いインドや他国への流れ、政府間の国際協力だけでなく民間企業の取組についても要検討。→需給差は切り取り方で見方が変わるが、今後も広くアジアで検討する。
【第二発表】移住労働者の送出社会と受入社会の有機的な繋がりがもたらす持続可能性 -高知県とフィリピン・ベンゲット州の姉妹県州協定を活用した技能実習生の実践
発表者
- 二階堂裕子(ノートルダム清心女子大学)
コメント・応答
- 「移住システム論」を「自治体媒介型移住システム」から新たに捉え直した点は意欲的。
- 地方自治体とアジア諸国の関係強化に着目したのは、移民研究では新しい視点であった。
- 受入国・送出国の両方で調査されることで、移住を線で追いかけることが可能となった。
- 国家間・中央行政の制度が語られがちな移住政策を、自治体レベルでの媒介構造として分析している点に新規性がみられる。
- 具体的な地域を対比しながら、双方向的な視点から、移住制度の現場レベルでの実態が丁寧に記述されている点は評価できる。
- 制度全体への信頼と、関係者個々人への信頼とのギャップに注目した分析は独自性が高く、説得力がある。
- 特定の移住者の逸脱行動が、制度全体に負の影響を与えるリスク構造を可視化し、制度の脆弱性や責任構造に焦点を当てている点が評価できる。
- 開発学の知見を適用する可能性に係る検討を期待。(例:米倉雪子(2022)「カンボジア農家の移住労働に代わる生計改善策に関する一考察」『国際開発研究』31(1)、pp.35-54)
- 追跡調査による技能移転(新しい栽培技術)の内容(質)を明確化したい。(例:ビニールハウス、接ぎ木、水耕栽培、小型耕運機が挙げられたが、何がどのように可能になるのか。)→今夏、フィリピンでの調査を予定しており、さらに詳細な情報を収集する予定である。
- 自治体媒介型移住システムの一般化がやや限定的、なかには悪質なパターンもあるのではないか。他地域との比較や汎用性が不足している。→今後、他の事例についても検討を重ねていきたい。
- 行方不明者の原因分析が制度側に寄っている印象がある。逃亡せざるを得ない状況にある技能実習生もいる。そうした社会的労働的要因への言及があれば、よりバランスのとれた分析になるのではないか。
- 制度の自明性、つまり自治体が関与するから正当であるという前提が自明化している。その正当性の根拠や限界への批判的検討が不足している。
- 自治体媒介型移住システムについては魅力を感じるアプローチだと考えるが、一方で多人数に対応できないという問題もあるので、別の制度設計でも補完するアプローチ、たとえば、もっと過疎地域で送出機関に活動してもらう、といった方向も考えられるのではないか。
- 現行の技能実習制度であるから、この自治体媒介型移住システムがうまく作動している可能性もある。育成就労制度に移行した場合はどうなるのだろうか。→自治体媒介型移住システムという概念は、今回の報告で初めて検討を試みたもので、今後さらに事例を追究していくなかで検討を重ねていくつもりである。高知県とベンゲット州の協定の事例は、1975年からの長い歴史をもつもので、普遍化が難しい可能性がある。この点についても、これから検証していきたい。
総括
- セッションの狙いどおり、送出国と受入国の双方を視野に入れた開発協力の在り方について、中央政府と地方自治体という視点をバランスよく発表者で分け合いながらも、労働移民の主体性を尊重するという意義については共通して論じることができ、開発研究と移民研究を架橋した議論を行うことができた。
- 最後に「ブローカー」に関して高度人材の受入れにおいても課題となっていることが、コメンテーターの松下会員から提起され、本研究がさらに展開する可能性の高さもうかがえた。
- 朝一のセッションにもかかわらず、ご参加頂き、質問やコメントまでくださった皆様には本当に感謝です。
報告者(所属): 石丸大輝(国際協力機構)、二階堂裕子(ノートルダム清心女子大学)
B2:アフガニスタンへの支援を考える
- 開催日時 6月21日 11:10 - 13:10
- 聴講人数:約20名
- 座長・企画責任者:嶋田晴行(立命館大学)
- コメンテーター・討論者:髙橋基樹(京都大学 名誉教授)、岡野内正(法政大学)
【第一発表】アフガニスタンにおける人間の安全保障の実現に向けた課題~持続的な開発への挑戦~
発表者
- 服部修(JICA)
コメント・応答
- タリバーンやアフガニスタンの歴史・文化・民族の特性を考察した上で支援アプローチを考えるべき、複合的な危機が頻発する世界情勢を踏まえつつ、国家建設では人造りだけでは不十分であることも理解した上でのODAのアプローチを考え直す分岐点に来ている、JICAは人道支援と開発支援をつなげる重要な役割を持っており、人道支援含めてそのアプローチを検討していくべきとのコメントに対し、JICAは法的には人道支援機関ではないが緊急援助隊含め工夫次第で人道支援と開発支援をつなぐことができる援助機関であり、JICAにできることを今後も考えていきたいと回答。
- これまでの対アフガニスタン支援への評価、さらにアフガニスタン人は日本も米国も同等に見ているのかとの問いに対し、「成功」と「失敗」は何をもって判断するかにより解釈が異なる。重要なのは過去の支援を検証し今後の支援へ活かしていくことである。過去の経験と昨今のアフガニスタンとの関係から考えると、アフガニスタン人は日本人・日本を信頼していると感じる。それは米国に向けられるものとは別物であると考えると回答。
【第二発表】危機下のアフガニスタンにおけるノンフォーマル教育の意義と今後の支援の可能性 -女子・女性の教育をいかに継続できるか-
発表者
- 小荒井理恵(教育協力NGOネットワーク)
コメント・応答
- 時に権力側に利用される可能性もある女性への教育支援についてどのように考えるかというという問いに対し、教育、特に女子・女性の教育はセンシティブで政治的な文脈で利用されてしまう懸念もあるが、最大限留意しつつ、現地の人々が女子教育の継続を望んでいるため、あらゆるチャンネルを通じて継続する必要があると回答。
- 支援対象のサンプル数の問題として学校へ行きたいという声ばかりではないのではないか、どの程度の広がりがあるのかとの問いに対し、限られた人数のデータではあるのは指摘のとおりであるが、これまで学校に行きたくないという声は個人的にはアフガニスタンで聞いたことはない。家族が反対することはあるが、その場合はコミュニティが家族を説得する等の取り組みも以前あった。広がりについては、現地の最新状況の把握には限界があり明確な回答はできないが、様々な学習の取り組みがあると回答。
【第三発表】未承認国家への援助パラドックス-タリバーン「政権」と援助
発表者
- 嶋田晴行(立命館大学)
コメント・応答
未だいずれの国家・国際機関から未承認状態にもかかわらず、人道援助という名で支援が継続されているタリバーン政権下のアフガニスタン支援の今後、開発支援と人道支援の区別自体に意味が無いのではとの質問と指摘に対し、現在、欧米では援助そのものへの見直しの機運が高まっており、それは援助を再考する機会でもあり、アフガニスタン支援はその中の一つのケースとして取り上げることが考えられると回答。
総括
JICA、NGOでアフガニスタン支援に携わる実務者、かつてアフガン支援へ従事し現在は大学に在籍する研究者による発表は、現在に至るまでの対アフガニスタン支援の成果と課題を浮き彫りにするものであった。長年にわたって援助を研究テーマの一つとしてきた知識・経験とも豊富な2名のコメンテーターからの質問、示唆は根本的かつ前向きなものであり、発表者たちの今後の活動・研究を励まし刺激を与えるものであった。本セッションを着想した際の動機である、過去の日本の莫大な対アフガニスタン支援を振り返りその教訓を今後の援助へ活かすための第一歩として意義あるセッションであった。
報告者(所属): 嶋田晴行(立命館大学)
B3:新興国の台頭と国際開発レジームの変容
- 開催日時 6月21日 14:10 - 16:10
- 聴講人数:約20名
- 座長・企画責任者:稲田十一(専修大学)
- コメンテーター・討論者:山形辰史(立命館大学アジア太平洋大学)、小林誉明(横浜国⽴⼤学)
【第一発表】途上国債務再編の国際的枠組みと中国の対応 -「分散化」か「収斂化」か?―
発表者
- 稲田十一(専修大学)
コメント・応答
本報告は、欧米などの主要先進国や世銀・IMFを中核とする伝統的な国際開発金融体制に対して、中国の台頭がもたらすインパクトとその変容過程に焦点をあてたもの。討論者の山形会員より、国際開発レジームの「収斂化」は「分散化」の事後処理対応ではないか、中国だけではなく、欧州諸国やBRICSの独自の動きも視野にいれる必要があろう、といった指摘があった。また、フロアより、近年の途上国の債務の拡大は、民間債務の拡大が大きく、この現象をどう見るか、等の質問があった。
【第二発表】多国間援助に対する湾岸ドナーのアプローチ ―規範・利益・国際開発レジームへの示唆―
発表者
- 近藤久洋(埼⽟⼤学)
コメント・応答
本報告は、制度化が進んだ国際開発レジームとして多国間援助に注目し、湾岸ドナーが自身の多国間援助を形成しながら、他者が形成してきた多国間援助になぜ、どのように接近してきたのかを分析したもの。討論者の小林会員より、湾岸ドナーによる多国間援助の枠組みは、国際開発レジームの中でどのような位置づけになるのか、援助レジームと開発レジームの関係は、地域的枠組みの位置つけは、等の疑問が提示された。座長の稲田会員より、「レジーム」は国際関係論の議論であり、一国も地域組織も国際機関も独自の利益・規範を有するアクターとしてとらえる、等のコメントがあった。
【第三発表】先進国主導の開発援助秩序の自壊 -「グローバルな法の支配」の見地から-
発表者
- 志賀裕朗(横浜国⽴⼤学)
コメント・応答
本報告は、開発援助秩序の変容を検討するための理論枠組みとして「グローバルな法の支配(global rule of law)」の概念を導入し、この理論枠組みのもとで、開発援助秩序はどのような制度として評価されるのか、それはいつからどのように変容してきたのかを検討したもの。討論者の山形会員より、志賀報告は「先進国主導の開発援助秩序は自壊しつつあり、この問題はグローバルな法の支配の確立によって対処すべき」との論調であるが、履行強制が弱いグローバル社会において法の支配に多くを期待できないのではないか、等の疑問が提示された。多くの重要な論点が出されたが、時間の制約で、詳細な議論はできなかった。
総括
2時間のセッションに三つの報告であるため、1報告に付き40分の持ち時間で報告・コメント進め、フロアからの質問時間も多少とることができた。それでも、各報告とも多くの論点を含んでおり、議論を十分に行うことができたとは言い難い。今後、また別の機会に更に議論を進める機会があることを期待する。
報告者(所属): 稲田十一(専修大学)