
関西支部(2025年2月)
2024年度、関西支部ではハイブリットによる定期的な研究会の開催を計画しました。 本支部が開催する研究会では、国際開発・国際協力に関するさまざまな分...
Recent Updates

2024年度、関西支部ではハイブリットによる定期的な研究会の開催を計画しました。 本支部が開催する研究会では、国際開発・国際協力に関するさまざまな分...

このたび津田塾大学 総合政策学部で下記のとおり専任教員を募集しております。 募集要項 分野 経済学、准教授または専任講師(任期なしの常勤):1名 着...

Kyoto Environment and Development Seminar #41 (Joint with the 44th Resilie...
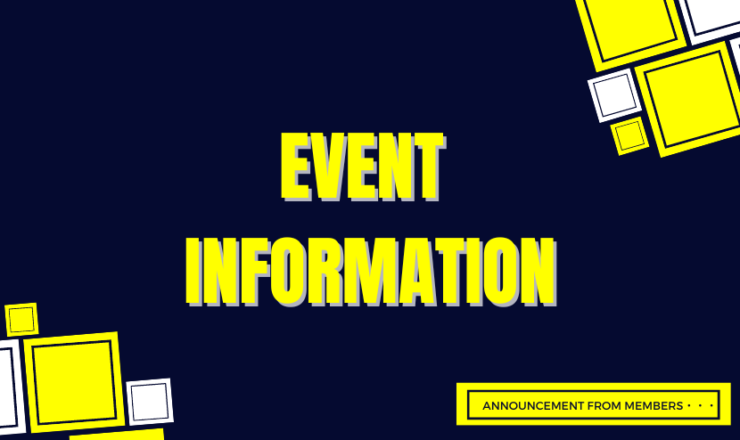
国際セミナー:「人新世:持続可能な開発に向けたインドネシアの協同組合の強化」 AGENDA ON INTERNATIONAL SEMINAR “AN...

D2:ここから始める「デジタル技術の国際開発への活用」 開催日時:6月15日13:45 - 15:45 聴講人数:約15名 座長・企画責任者:狩野 ...

関西支部:2024年度6月末活動報告 2024年度、関西支部ではハイブリットによる定期的な研究会の開催を計画しました。 本支部が開催する研究会では、...
![社会課題解決のための開発とイノベーション [FY2022-]](https://jasid.org/wp/wp-content/uploads/2021/11/eye-Solving-Social-Problems-740x440.png)
2024年度活動報告書 研究部会活動概要 2024年度においては、本部会の3年度として、今まで2年間に、外部講師を招聘して実施した研究部会セミナーで...

43rd Professional Statistical Analysis Workshop: Basic and Advanced techni...
![社会課題解決のための開発とイノベーション [FY2022-]](https://jasid.org/wp/wp-content/uploads/2021/11/eye-Solving-Social-Problems-740x440.png)
We are pleased to inform you of our online research seminar of this year. ...

SDGs推進の先を見据えたZ~α世代グローバルリーダーの育成:国際パネルディスカッション 2030年ゴールに向けた中間点を過ぎ、世界的にSDGs17...

関西支部では下記の研究会をハイブリットで開催します。 ご参加を希望される方は関西支部事務局までご連絡ください。 Zoomアドレスをご共有させていただ...

Another KED seminar is taking place at 1:00pm next Saturday. Kyoto Environ...

ラウンドテーブル [1I01] 国際教育開発のシングル・ストーリーを乗り越える:実務者と研究者の出会い直しに向けて 日時:2023年11月11日(土...

活動報告 1-1 若手研究者報告会の開催(JASID Tokai 2023 Conference for Young Researchers) 日時...

2023年度、関西支部ではハイブリット形式またはオンライン形式による定期的な研究会の開催を計画しました。 本支部が開催する研究会では、国際開発・国際...

Kyoto Environment and Development (KED) Seminar is taking place at 3pm thi...

関西支部では下記の研究会をZoomで開催します。ご参加を希望される方は関西支部事務局までご連絡ください。Zoomアドレスをご共有させていただきます。...

関西支部では下記の研究会をZoomで開催します。ご参加を希望される方は関西支部事務局までご連絡ください。Zoomアドレスをご共有させていただきます。...

共立女子大学国際学部では、英語教育プログラム「GSE (Global Studies in English」を主担当の教員(Global Studi...

活動報告 関西支部では国際開発・国際協力に関するさまざまな分野の専門家を招聘し、世界的な問題となっているコロナ禍、また、コロナ後における国際開発・国...

関西支部では下記の研究会をハイブリットで開催します。ご参加を希望される方は関西支部事務局までご連絡ください。Zoomアドレスをご共有させていただきま...

The Resilience seminar cordially invite you to join the seminar. The 42nd ...

Kyoto Environment and Development Seminar #22 Date & Time: June 22, 20...

International Workshop on “Asian urbanism and urban informality” With rapi...

The Kyoto Environment and Development Seminar cordially invite you to join...

The Kyoto Environment and Development Seminar cordially invite you to join...

The Sustainability, Economics, and Ethics (SEE) Research Group at Universi...

ECFAでは、昨年に引き続き、(株)レックス・インターナショナル会長、橋本強司氏をゲストに迎え、オンラインセミナーを開催します。今回のテーマは未来都...

第5回研究部会を2023年3月18日(土曜)15:00~にて開催いたします。ハイブリッド開催の予定です。ぜひご参加いただけましたら幸いです。 開催要...

近年、温暖化等の地球環境問題、COVID-19の世界規模の感染拡大、突然のロシアのウクライナへの軍事侵攻、米中覇権争いといった深刻な課題により、政治...