
開催案内「第26回国際ボランティア学会大会・シンポジウム」2月...
2月22日(土曜)に近畿大学で国際ボランティア学会第26回大会を開催いたします。 また大会の午後には、「忘れられた人道危機」に関する公開シンポジウム...
Recent Updates

2月22日(土曜)に近畿大学で国際ボランティア学会第26回大会を開催いたします。 また大会の午後には、「忘れられた人道危機」に関する公開シンポジウム...

この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。

この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。

この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
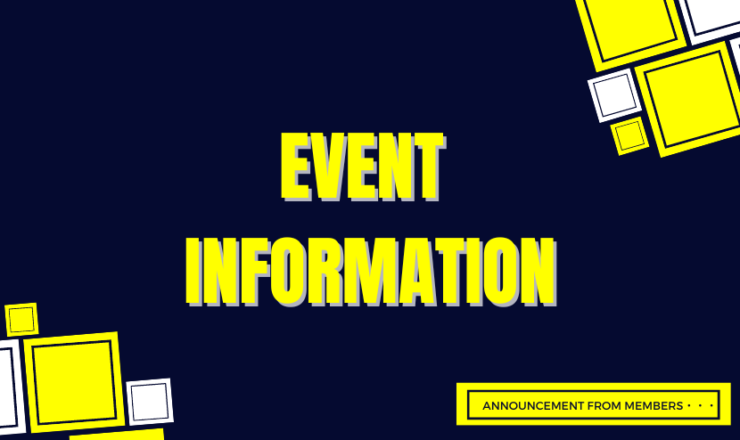
緊急人道支援学会は第二回大会を2025年2月1日(土曜日)早稲田大学本キャンパスで開催します。 昨年度第1回目の開催から1年を経過する現在においても...

Planning and Management 支部・研究部会活動、特別事業の企画運営および合理的配慮等 委員長 会長:山田肖子(名古屋大学) 委員...

Planning and Management: JASID Reasonable Accommodation 障害を持つ会員への合理的配慮について...

Conference Organization 全国大会および春季大会の企画運営等 委員長 松本 悟(法政大学) 工藤尚悟(国際教養大学)*共同委員...

Election Administration 国際開発学会では、3年に1回 理事候補の選挙を実施します。学会員全員(学生会員も)に選挙権があり、次...
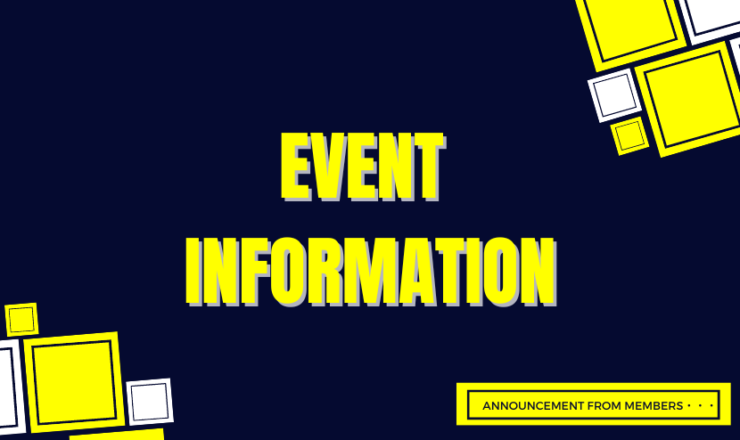
日本出版学会 翻訳出版研究部会のご案内(2024年9月27日開催)「専門書翻訳をアートする――翻訳のプロでない者にできること」 日本出版学会 翻訳出...

総括 国際開発学会第25回春季大会は、2024年6月15日(土曜)に宇都宮大学を会場に対面(一部オンライン)にて開催し、16日(日曜)には、エクスカ...

オプション1:「足尾銅山問題を通じて開発を考える」 2024年6月16日(日曜)08:30~17:00 於:足尾銅山観光―古河歴史館―植佐食堂(講話...

この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。

この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。

トゥーサン・カファイレ氏特別講演「コンゴ民主共和国上カタンガ州における鉱山労働者の状況と改善に向けた方策」 7月23日にコンゴ民主共和国出身のトゥー...

日本評価学会-社会実験分科会では、今年で5回目となる研究報告会2024を開催致します。 参加無料ですのでぜひご検討ください(Zoom視聴、および早稲...

世界思想社の「学ぶひとのために」シリーズの定番のテキストを全面改訂し、『国際協力を学ぶ人のために』がこの5月に刊行となりました。 昨年9月に急逝され...

第12期の選挙管理委員会では、第11期に引き続き、学会理事の仕事および理事選挙の仕組みについての広報活動を担う「学生せんかん幹事」メンバー若干名を、...

『エビデンスに基づく実践のグローバルトレンド』+自由論題3本 過去4年連続で実施しております社会実験分科会の研究報告会を今年度も実施致します。 昨年...

この度、『代替社会経済に向けて―「二十世紀の意味」を出発点として』を、個人出版しました(DTP出版、定価1,500円+税=1,650円)。 私の、4...

国際開発学会と法政大学国際文化学部共催で開発協力大綱に関するシンポを開催します。ぜひご参加ください。 開催概要 日時:2024年2月24日(土曜)1...

2023年11月の総会で12期会長を拝命しました名古屋大学の山田肖子と申します。 2026年総会まで、約3年間、皆様に気持ちよく、やりがいを持って関...

プレナリー(対面・オンライン) 日本の開発援助はどこに向かうのか―開発協力大綱の改定を受けて— 2023年11月11日(土曜)13:30 〜 16:...

国際開発学会第12 期:委員会の構成および幹事の委嘱 委員長 山田肖子(名古屋大学) 委員 副会長、常任理事、本部事務局長、本部事務局次長 企画運営...

国際開発学会第12 期:委員会の構成および幹事の委嘱 委員長 山田肖子(名古屋大学) 委員 副会長、常任理事、本部事務局長、本部事務局次長 企画運営...

2023年度活動報告 明治大学を開催校とし(島田剛実行委員長)、第33 回全国大会を開催した(2022 年12月3 日、4 日;対面・オンラインのハ...

2024年度より、以下の3委員会を統合し、新たに「社会共創委員会」を設置することとなった。 統合前の各委員会の昨年度の活動報告は以下のとおり。 20...

この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。

この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。

この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。