
開催案内(会員・一般):COP30セミナー12/19「気候変動...
<COP30フォローアップセミナー> 「気候変動と水」COP30合意と関連取組の最前線 ~日本政府・ビジネス・海外ゲストを交え、今後を展望する~を1...
Recent Updates

<COP30フォローアップセミナー> 「気候変動と水」COP30合意と関連取組の最前線 ~日本政府・ビジネス・海外ゲストを交え、今後を展望する~を1...

【JICA セミナーのご案内】 12/19(金)開催:南アジアおよび東南アジアにおける障害者包摂型イノベーション Seminar on Disabi...

上智大学アジア文化研究所は、12月21日(日)10時~12時に標記のセミナーを対面とオンライン併用で開催します。英語と日本語併用で行いますが、あいに...
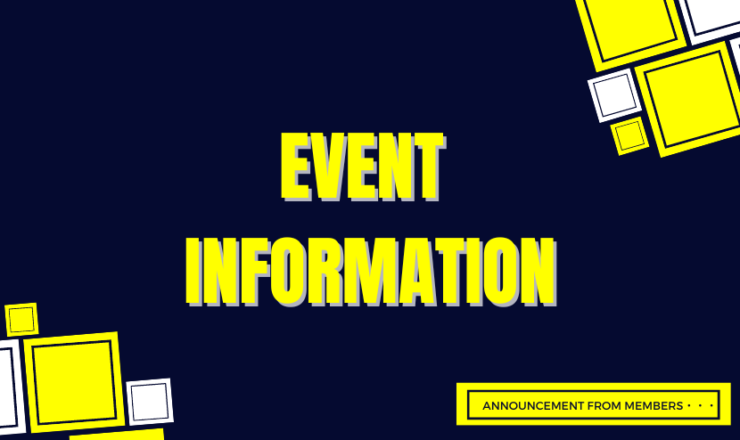
グローバル・ニュース・ビュー(GNV)は、世界の問題・課題についてより多くの人が知ることが、解決のための第一歩であるという目的意識から、大阪大学の一...

学会員の大野泉です。いつも貴重な情報を共有いただき、ありがとうございます。この度、JICA緒方研究所にて、『途上国の産業開発と日本の経験―翻訳的適応...

広島大学の坂田と申します。12月8日(月)に、ガーナで下記セミナーを開催いたします。日本時間の夜開始となってしまいますが、入退場はご自由にしていただ...

会員各位、 早稲田大学にて、下記講演会を開催予定です。是非ご参加下さい。 ① International Workshop:11月28日(金) Ti...

【今年最後の開催】(11-12月期) IDCJ『プロフェッショナル統計分析ワークショップ』(応用4コース) 高度な分析テクニックをわかりやすい手計算...

This seminar presents preliminary findings from ongoing joint research by ...

国際開発学会の皆様 いつも有益な情報をありがとうございます。国際開発センター(IDCJ)では以下のワークショップを開催致します。この機会にぜひご参加...

世界銀行グループ 大学院生向けキャリアセミナー 世界銀行グループ2025年日本人採用リクルートミッションにあたり、世界銀行グループの採用チームが来日...
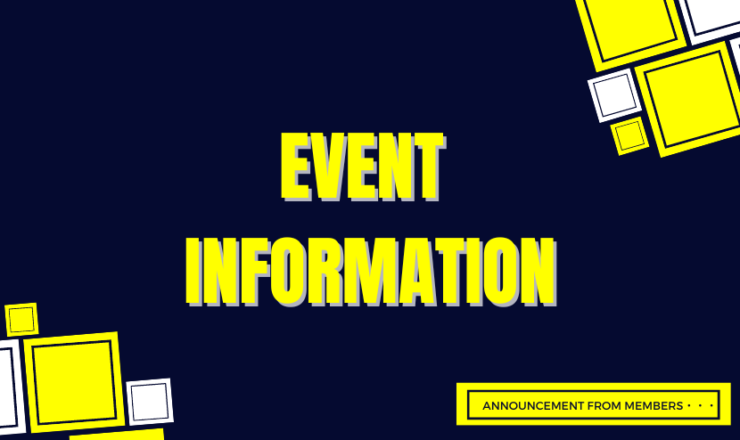
We are delighted to invite you to the second session of the ‘CICE Li...

Sophia Open Research Weeks 2025 企画オンラインセミナーのご案内です。 タイトル:移民女性の目線で日本を見直す『外国人...

グローバルキャリアセミナー「技術・専門性で世界に貢献する~開発コンサタント~」(10/24) @高知大学 ECFAでは開発コンサルタントについて知っ...

マレーシア科学大学(Universiti Sains Malaysia)主催(日本財団マレーシア後援)のセミナーへのご招待です。 「グローバルな移住...

国際開発学会の皆様 いつもお世話になっております。 国際基督教大学の西村幹子です。 本学では、以下のとおり、ケニアの障害児施設を運営する公文和子さん...

教育関係者・多文化共生や国際理解教育にご関心のある皆さま 初めまして、株式会社パデコの宇野耕平と申します。 私たちは教育分野での国際協力や教材開発な...

【2025年12月開催】 第49回プロフェッショナル統計分析ワークショップ (開催日:12/15,17,19、対面参加&Zoom参加のハイブリット開...

会員の皆さま 平素よりお世話になっております。ECFA河野です。 一般社団法人 海外コンサルタンツ協会(通称:ECFAエクファ)では、途上国支援のプ...

【オンライン開催】10/4(土)第2回ATFJセミナー 『 中国における脱炭素社会構築に向けた自動車電動化の取組みと展望 』 https://atf...

下記の要領で「開発と社会学」(移住と開発編)の参加者を募集します。ご関心のある方はご応募下さい。今期は「移住と開発」に特化した課題図書をとり上げ、開...

「みんなのSDGs」(https://www.our-sdgs.org/)と「おたがいハマ」(https://otagaihama.localgoo...
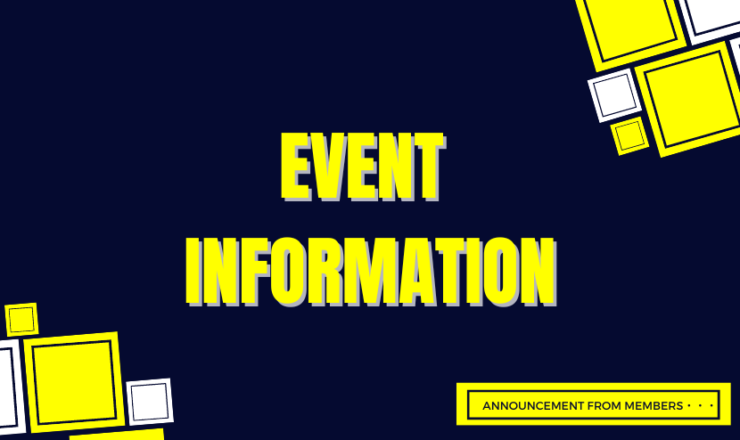
国際開発学会学会員の皆様 わたくし自身も参加予定の本研究集会につき、国立民族学博物館の松井梓さんから下記のご案内をいただきましたので共有します。ふる...

アフリカにおいてソリューションをもたらす可能性を秘める大阪・関西の企業とアフリカとの、ビジネスを通した先駆的な関係構築を促進すべく2022年から東大...

活動報告(2年目) 「開発論の系譜」研究部会では、おおむね2か月に1回の頻度でオンライン研究会を行ってきた。活動1年目ということで部会設置時の賛同者...

『社会課題解決のための開発とイノベーション』研究部会 Innovation and Development for Solving Social P...

2025年6月、明石書店より刊行されました、『エリアスタディーズ215 イエメンを知るための63章』につきまして、編著者の佐藤寛先生、馬場多聞先生、...

We, CICE, IDEC Institute, Hiroshima University, are holding the following ...

独立行政法人国際協力機構(JICA)緒方貞子平和開発研究所(JICA緒方研究所)および地経学研究所は、7月23日(水)に、ウェビナー「揺らぐ開発協力...

JICA緒方研究所では、開発協力に関する国際的な動向や知見を多様な関係者で共有・相互学習し、新しいアイデアを生み出すKnowledge Co-Cre...