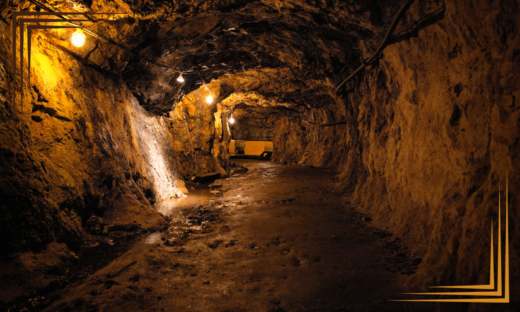第26回春季大会報告:一般口頭発表-G

一般口頭発表
G1:制度を作る、制度を使う:開発戦略・災害対策・制度化過程
- 開催日時:6月21日9:00 - 11:00
- 聴講人数:約15名
- 座長:小山田英治(同志社大学)
- コメンテーター・討論者:花岡伸也(東京科学大学)、小山田英治(同志社大学)
【第一発表】地域・辺境のニーズを取り残さない ーJICAによるドミニカ共和国・国家開発計画システムの適用支援プロジェクトー
発表者
- 和田泰志(アイ・シー・ネット株式会社)
- 中川圓(アイ・シー・ネット株式会社)
コメント・応答
ドミニカ共和国における国家計画・公共投資システムの全国的な適用を支援するJICAのガバナンス支援プロジェクト(PRODECARE)を取り上げ、プロジェクト形成における学術との接続の重要性を報告した。同プロジェクト成果として開発評議会設置・市開発計画策定手法の共通手法化、地域ニーズ登録システム導入、直接的な予算反映、住民参加と社会変革の促進を実現させた。そのなかで民主主義推進、中央政府・地域市民のバランス性、地域性の配慮、ポピュリズム抑制、制度運営の透明性確保などにおける学術的・理論的認識を理解しつつプロジェクトを進める重要性について強調した。それ対し以下のコメントと質問があった。①地域ニーズ登録システムの課題や限界について、②直接的な予算反映⇒市民参加・地域の声を反映できる成功事例と言える一方で、地方の政治家の役割はどうなっているか、③「5つの理論的柱は、プロジェクトの実践に総合的に組み込まれていた」「学術知見を実践に橋渡しした好例」とあるが、表現上の因果関係に注意が必要。プロジェクト成果・学びを既存の理論で裏付け可能にする説明の必要性がある。
【第二発表】独立後のキルギス政府による国家開発戦略の分析(2000-10年)
発表者
- 富樫マハバット(同志社大学)
コメント・応答
本報告では、2000-2010年のキルギス政府の国家開発戦略を3つの時期に分け取り上げ、①キルギス政府の現状と問題意識、②実現可能性(財源等)、③連続性や断続性の有無、④評価や検証体制について分析を行った。そこでは、全期間を通じて国際ドナー機関のアドバイスと影響は大きいこと、開発戦略では財政的な見通しや裏付けは見受けられないことを明らかにした。また政変による政権の断絶があっても、国家開発戦略においては連続性が確認されているとしている。そして、政府が国内外に自国の開発問題を認識し、ビジョンを設けること自体に一定の意義があることを主張した。それに対し、コメントとして、開発戦略実施における外部評価の不在、政策決定や開発戦略策定時のNGO参加における政治性の有無、汚職取り組みの有用性、そしてドナー機関の主要省庁への専門家派遣の実情に伴う間接的影響等について触れられた。
【第三発表】The Impact of Township Development on Local Communities: Empirical Evidence from Kabul, the Capital of Afghanistan
発表者
- Zawad Mohammad Farid(Nagoya University)
コメント・応答
アフガニスタン・カブールにおける都市化と土地収奪の関係を、モハマディア・タウンシップ(MT)を事例として報告した。難民帰還民や国内避難民(IDP)の急増が都市化を促進し、脆弱なガバナンス体制や土地所有のインフォーマル性により有力者による違法な土地取得や収奪問題が生じ、タリバン政権前後を通じて地域社会に深刻な悪影響を与えている実態を、インタビュー調査を通じて明らかにした。Harveyの「収奪による蓄積」理論をカブールの事例に応用することで、批判的都市化理論の射程を拡張している。報告では、①都市土地法の制度改革と法執行の強化、②タウンシップ開発手続の簡素化と行政的監視の強化、③慣習的土地所有を認める包括的かつ包摂的な土地登録制度の構築、④公平で持続可能な都市開発に向けた地域社会の計画参加の制度化を唱えている。コメントでは、インタビュー調査に重きを置きすぎた結果として、収奪的政治経済構造の分析が不十分という点が指摘された。また、インフォーマル性は脆弱なガバナンス下において多くの国で見られる共通の現象であり、提言は重要であるものの一般的であり、今日のアフガニスタンにおいてこの問題解決にどう対処すべきか報告者自身の立場・考え方の再確認が求められた。
【第四発表】Socio-Economic Vulnerability due to Flood and Planning of Early Warning System: Disaster Risk Reduction to its Management
発表者
- Rao Muhammad Amir Akram (Toyo University)
コメント・応答
パキスタン・シンド州ダードゥー地区における農村部および低所得都市地域住民の洪水による社会経済的脆弱性をサーベイ調査(人口統計、経済状況、住宅インフラ、復旧・対応力、災害への認識等)を通じて現状を報告した。住民の生計、インフラ、地域社会の福祉に多大な混乱が生じており、とりわけ農業分野と小規模事業者が深刻な影響を受け、住居の被害、人々の避難、医療や教育などの基本サービスへのアクセスの制限も広範囲で確認された。また低所得層、女性、子どもなどが最も厳しい状況下にあり、復旧支援も資源不足や支援の遅延により非効率であることを明らかにした。地域住民の回復力や非公式な相互扶助の仕組みが存在するとはいえ、長期的な復興には、的を絞った支援策、インフラの強化、持続可能な災害管理戦略の必要性があるとした。報告に対し、調査結果を明確に示す重要性、脆弱性の定義、女性の被害度合いの説明、調査手法についての質問とコメントが出された。
総括
本セッションでは、「制度を作る、制度を使う」テーマで、開発協力、開発戦略、災害対策、土地収用に関するアプローチからそれぞれ報告がなされた。制度を活用して開発を推進できた例、制度構築を開発戦略の優先事項として策定された例、制度は存在するもののうまく機能していない例と、それぞれ異なった内容の報告であった。開発・制度という共通課題からは、制度は適切に機能してはじめて開発や民主化が達成可能であるということが再認識されたのではなかろうか。そういった意味において、本セッションは有意義、かつ報告者が互いに多様な事例を理解することを可能としたセッションであったと考える。
報告者(所属):小山田英治(同志社大学)
G2:多様性の中の共存―資源にまつわる社会と持続性
- 開催日時:6月21日11:10 - 13:10
- 聴講人数:約25名
- 座長:池上甲一(近畿大学)
- コメンテーター・討論者:池上甲一(近畿大学)、西川芳昭(龍谷大学)
【第一発表】共有資源管理に関する協力は市場アクセスによって変わるか?―モンゴルの牧畜民に対する公共財ゲーム実験―
発表者
- 鬼木俊次(国際農林水産業研究センター)
コメント・応答
本報告は、モンゴルにおける草地の資源管理を担う牧畜民を対象に行った公共財ゲーム実験の結果についての分析結果である。人口圧の増大と都市部からの距離の遠さが協力の可能性を高める要因となっていること、研修によって協力関係は再構築される可能性があることの2点が結論として興味深い。
主なコメントと応答:①本研究はコモンズ研究として位置づけ可能である、②その観点から、草地を対象とする特異性と共通性は何か、③草地はオープン・アクセスの準公共財として捉えるよりもクラブ財として捉える方が妥当ではないか、④モンゴルの草地管理の実相を知りたいなどが指摘された。発表者はこれらのコメントを踏まえて、学会誌に投稿したいとの応答があった。また草地利用について用益権はあるのかという参加者からの質問に対して、用益権的なものはあるし、一部には社会主義の歴史の影響もあるとの回答があった。
【第二発表】コモンズと乱伐の狭間で―ルーマニアの森林利用に見る住民利用と森林保全のせめぎ合い―
発表者
- 浅田直規(国立民族学博物館)
コメント・応答
本報告は、ヨーロッパ最大級の原生林を持つルーマニアを調査地として、経済的価値に収斂しきれない「文化的価値」が違法な利用を内包しながらも生活全般に入り込んでおり、そのことが森林保全の誘因となっている可能性があること、生業的側面を持つレジャー活動などが「文化的価値」の継承に役立つ一方で、伝統的知識と行動との間に乖離が生じ、コモンズとしての性格を失っていく可能性があることを指摘した。特に若者世代における利用法の形式化が、使用の文脈で生じるコモンズの内的崩壊に繋がりうるとの指摘は重要な示唆に富んでいる。
主なコメントと応答:①旧社会主義国のコモンズ利用を経済的議論と異なる視点から分析したことを高く評価、②現地NGOの出自と構成についての詳細は?、③貨幣価値と文化的価値のバランスを判断する基準は? 発表者から、NGOは当初ドイツからの資金に依存していたが、次第に現地化・独立傾向を強めた、③は今後の課題だとの応答があった。
【第三発表】マラウィ湖国立公園の飛び地集落における民族・社会的多様性と生計活動の関連性:自然保護区周辺地域の特異性と共通性の視点から
発表者
- 草苅康子(東京大学) ほか5名
コメント・応答
本報告は自然保護区域内の飛び地集落において形成された多民族共存が生み出す多様な生業複合の実相を紹介し、伝統的知識に基づく文化的規範的保全意識の存在を浮かび上がらせた。
主なコメントと応答:①包摂(民族的)とガバナンスの仕組みづくりの重要性(実践面)が本報告によって示唆された。②飛び地集落の構成要素(定義)とその特異性をどのように普遍化できるのか(対象事例の位置づけはいかに?)、②国立公園という保護区に住むことで生じ得る、伝統的資源利用と公的管理(法制度)とのせめぎ合いはどうなっているか。またフロアーからマラウィ湖の漁業管理制度と漁獲情報の詳細を知りたいとの質問が出た。発表者は②について、国立公園設置時につくられたガイドラインが、住民主導で明文化されるに至ったと回答した。また、このガイドラインの下で、在住住民が移住者を組織して木を伐採する取り組みが生まれているという新しい動きが紹介された。
【第四発表】手押しポンプの維持管理におけるジェンダーの影響
発表者
- 近藤加奈子(京都大学大学院)
コメント・応答
本報告は、導入された村落給水施設の管理組織に女性参加を求める国際的な言説に対して、モザンビーク農村の調査から「優良事例」でも女性参加の実質化には、女性の役割の固定化や財務上の意思決定に関与できない、メンテナンスなど重要な機能が特定の男性個人に集中といった多くの課題があること、同時に旧来の水利用で培われた女性の知恵を近代的管理に組み込む工夫が求められることを明らかにした。
主なコメントと応答:①在来の水源(日常知)と手押しポンプ(近代知)の間の対立をどう止揚しているか、②ポンプは利用者間、利用者と管理者の間で利害が衝突する場、とくに水のひっ迫条件下では権力の起点ともなるという視点も必要、③給水施設の維持管理をめぐるジェンダー問題の背景として教育と現金アクセスを挙げているが、それで十分か、④従来は「タダの水」→「お金を払う」ことに抵抗や戸惑いはなかったのか、⑤手押しポンプで水汲み労働はどれくらい軽減されたのか。またフロアーから、手押しポンプのメンテナンスに踏み出したメカニズム(言い出しっぺ、リーダーシップ)についての質問があった。発表者からは、高齢者や寡婦に対する利用料免除があり、柔軟に運営されている面もある、手押しポンプだけでは水需要を賄いきれず、とくに水待ち時間が長くなって水くみ労働が軽減されたと言い切れない面もある、手押しポンプの水は質が良いが、水量が十分とはいえないので旧来の水源も意味がある、といった応答があった。
総括
本セッションは昼食時間にあたる13:10までの開催時間となったが、参加者は途中で退場することもなく熱心に発表を聞き、また本様式に記載できなかった質問もあって、活発かつ刺激に満ちたセッションとなった。ほぼ予定時刻通りの発表時間であり、タイム・キーピングに協力してもらえたために、フロアーとのやりとりもある程度確保することができた。自由報告のグルーピングも適切であり、グローバル・サウスにおけるコモンズ研究の新しい領域と方法論の獲得に有意義だったと感じている。発表者にも概ね満足してもらえたと判断した。
報告者(所属):池上甲一(近畿大学)
G3:開発援助経験の輸出:アジア諸国の特色ある取り組みと国際比較
- 開催日時:6月21日14:10 - 16:10
- 聴講人数:約20名
- 座長:阪本真由美(兵庫県立大学)
- コメンテーター・討論者:Kim Soyeun(Sogang University)、吉田和浩(広島大学)
【第一発表】Unveiling the Dynamics of Rural Development: Saemaul Undong in Uganda
発表者
- Hyomin JUNG
コメント・応答
- 韓国で地域開発戦略として行われてきたSaemul Undong (セマウル運動)が、ウガンダの地域開発において広がりを持って定着つつある。セマウル運動が広がった背景には、ウガンダ政府のトップダウンのイニシアチブがあったものの、モバイル・スクールを活用したボトムアップ型の活動が評価されたことによるとの報告であった。
- コメントでは、セマウル運動の説明が十分ではなく初めて話を聞く人にはわかりにくいことや、研究命題をよりクリアにする必要があるとの指摘があった。
- 質疑応答では、韓国とウガンダのセマウル運動の相違はどこにみられるのか、他国で実施されている地域開発戦略との相違等についての質問があり、活発な意見交換が行われた。
【第二発表】From culture driven to localized knowledge driven: China’s evolving education policies and the ‘Luban Workshop’ in Africa
発表者
- Tinging Yuan、Ning Ma
コメント・応答
- 中国政府によるアフリカの教育に対する国際協力ついては、大学も主要なアクターとして実践されおり、近年では職業訓練を重視したルバン・ワークショッが行われている。これまでの中国政府による教育支援は、言語教育や孔子学院のような思想教育に重点がおかれてきたのに対し、ルバン・ワークショップは地域の人的資源の開発とそれによるケイパビリティに重点が置かれた新たな取り組みであるとの報告であった。
- コメントとしてはルバン・ワークショップのスキームの紹介だけでなく実践事例に踏み込んだ内容があると良い点や、ルバン・ワークショップにおける大学の関与の度合いを示すこと、これまでの中国の支援はマンパワー投入が中心であったものの、人材育成を通した実践可能な取り組みは重要であるとのコメントがあった。
- これからの人材育成の取り組み展開に期待するとのコメントがあった。
【第三発表】日本の国際協力における援助ロジックーオルタナティブな教育協力の可能性を問う
発表者
- 坂田のぞみ(広島大学)
- 朝倉隆道(広島大学)
コメント・応答
-
- 欧米による国際支援が自国をモデルとして、普遍的な開発モデルを提示するのに対し、日本の国際支援ではモデルを提示することは行われてない。日本の国際支援がどのようなロジックで展開されてきたのか、国際協力に携わるJICA職員へのインタビュー調査を通して当事者の視点から明らかにしようとした。調査の結果からは、日本の支援は日本型「モデル」や経験を押し付けることに躊躇しがちであり、被援助国のオーナーシップを重視、プロジェクトを持続的なものとしようとモデストなアプローチとして浸透しているとの報告があった。
- コメントでは、日本のアプローチについても、ある程度実績が評価されているプロジェクトについては「**モデル」と名前をつけて他国の実情に合わせて普及展開する事例が多く、「モデル」が存在しない訳ではないことや、トップダウン型のアプローチでも、ボトムアップ型のアプローチでも途中で意思疎通することなく中途半端な状況に置かれているものもあり、なぜ中間点で交差しないのか考える必要があるとの指摘があった。
【第四発表】災害復興を再構築するハイブリッドガバナンス:国際開発への含意
発表者
- 加藤知愛
コメント・応答
- 政府や企業、民間セクター、市民等が地理的・時間的境界を超えて協働して取り組む「ハイブリディティ」に着目。ハイブリディティが国内外で起きた災害復興においてどのように位置付けられてきたのか、既往研究のレビューを通して示した。また、国際開発にハイブリディティを位置付けることの重要性について、事前復興を中心にとした考察が行われた。
- コメントでは、復興計画におけるハイブリディティの重要性は評価するものの、災害は予測が難しい現象のため防災政策に対する優先度は下がりがちであり、さらに事前復興となると難しい現状がある。そのなかでどのように政策導入するのかというアプローチを示す必要があるとの意見があった。
総括
韓国・中国・日本が長期に渡り実践している国際協力に潜在するロジックを問う内容の報告が中心であった。これまでの国際協力研究では、欧米や国連を中心とする開発アプローチが主流となってきた、韓国・中国・日本等のアジア諸国による人材育成における協力実績が積み重ねられたことにより、それぞれの独自性を活かした新たなモデルが生まれつつある。ただし、長期間支援が行われているにもかかわらず、貧困解決や地域開発の達成が依然として難しい地域もある。それらの問題を解決するには、支援実施プロセスにおける地域のオーナーシップを確保することや、支援実施に際しての思想や理念も重要な要素となることが議論からは示された。
報告者(所属):阪本真由美(兵庫県立大学)