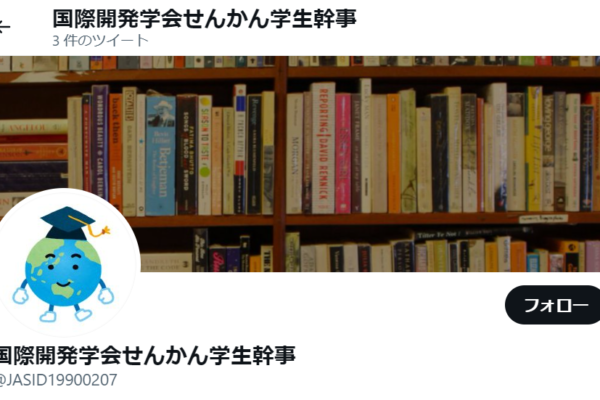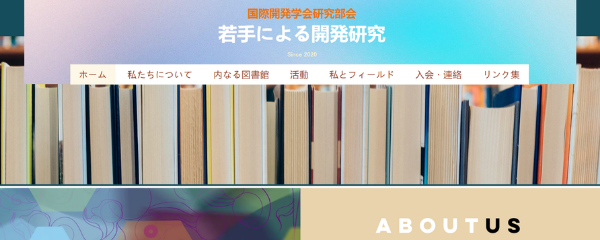委員会
COMMITTEES
賞選考委員会


保護中: 【会員限定】第35回・全国大会「優秀ポスター発表...

2024年度「国際開発学会賞」選考結果と受賞者のことば

賞選考委員会からのお知らせ(2025年2月)

賞選考委員会

【学会賞】2024年度『国際開発学会賞』作品公募のお知らせ

2023年度「国際開発学会賞」選考結果と受賞者からのことば

第34回全国大会「優秀ポスター発表賞」選考結果

賞選考委員会からのお知らせ(2024年2月)

第24回春季大会「優秀ポスター発表賞」選考結果

2023年度『国際開発学会賞』作品公募のお知らせ

優秀ポスター発表賞

【学会賞】2023年度『国際開発学会賞』作品公募のお知らせ
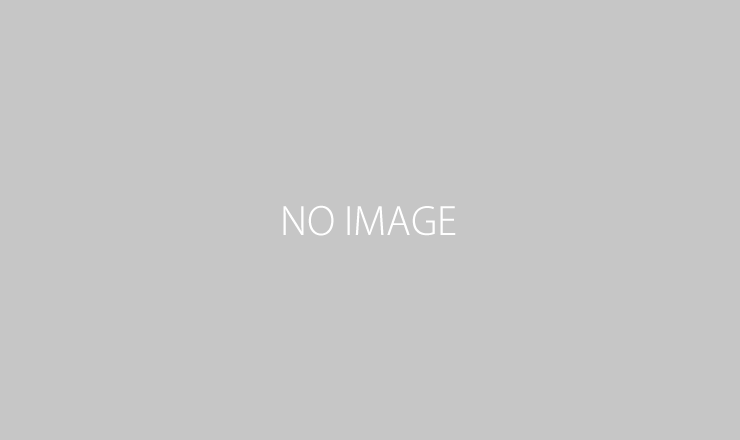
【公募】日本学術振興会「育志賞」受賞候補者の推薦について

2022年度「国際開発学会賞」選考結果と受賞のことば

第33回全国大会「優秀ポスター発表賞」選考結果

第23回春季大会・優秀ポスター発表賞

2021年度「国際開発学会賞」受賞者からのことば

2022年度「国際開発学会賞」作品公募のお知らせ
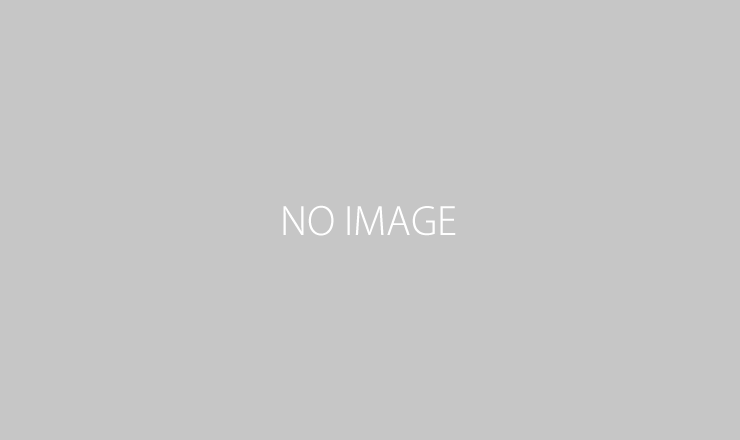
2022年度『国際開発学会賞』作品公募(6月30日まで)

これまでの受賞作品

2021年度「国際開発学会賞」選考結果

第32回全国大会「優秀ポスター発表賞」選考結果

賞選考委員会からのお知らせ(2021年11月)
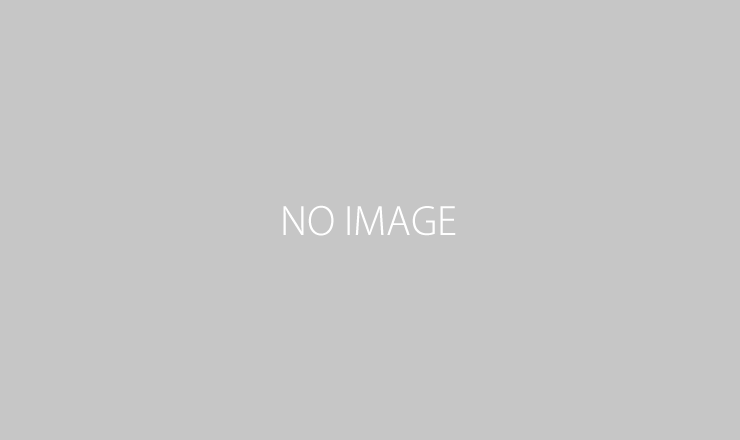
優秀ポスター発表賞(2021年度 春季大会)
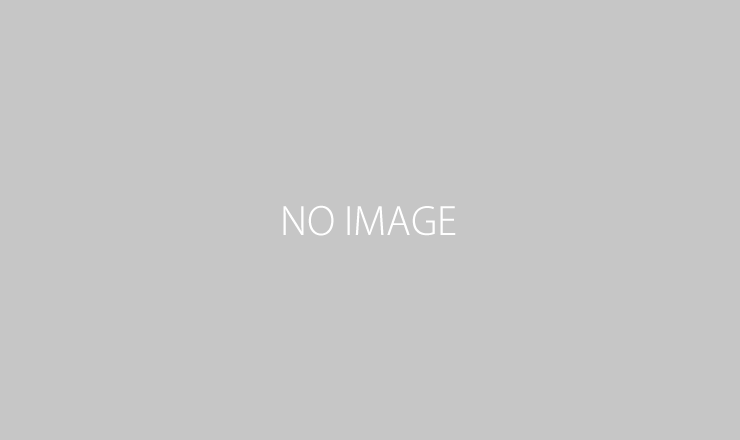
【公募】2021年度「国際開発学会賞」作品

学会賞

2020年度学会賞

優秀ポスター発表賞(2020年全国大会)

2019年学会賞受賞作品
- 1
- 2